固ゆで卵黄の作り方の注意!間違うと正しいアレルギー判断ができません

除去食が解除されて卵を食べ始めるとき、または離乳食で初めて卵を食べさせるときに一番最初に食べさせることが多い「かたゆでの卵黄」。
卵の黄身は白身に比べるとアレルギーの原因となるタンパク質を多く含みません。
また、卵は加熱によってアレルゲンとなるタンパク質が壊れる性質を持っています。
この2つの理由から、初めての卵の摂取はかたく茹でた黄身部分を少量与えることが一般的となっています。
しかし、この「かたゆでの卵黄」、作り方を間違うと正しいアレルギー判断ができないので注意が必要なんです!
正しいかたゆで卵黄の作り方を体験談も交えて書いていこうと思います(^^)
負荷テスト後、初めて自宅で卵黄を食べた日のこと
1歳9ヶ月のとき、息子は卵黄の負荷試験をかかりつけの病院で受けました。
結果はみごとパス!
晴れて完全除去から卵黄のみは摂取してOKと先生から許しが出ました。
→負荷試験ってどんな風にするの?【ちゃおずの卵黄負荷テスト体験記】
負荷テストをパスすると、自宅でも卵黄を摂取させる日々が始まります。
週に3回、まずは3gを2~3週間、次は4gを2~3週間、5gを2週間~3週間…、と増やしていくように先生から指導して頂きました。
負荷テスト後、初めて家でかたゆで卵黄を食べさせる朝がやってきました。
ドキドキの気持ちが半分、そして病院でまったく症状が出なかったから大丈夫だろうという安心感半分で私はゆで卵を準備し息子に食べさせました。
喜んで食べてくれるだろう、という私の予想には反し、息子は卵黄を「べー」と吐き出しました。
そして「コホコホ」と何度か咳き込み、しばらくすると息子は口のまわりと首を掻き始め、みるみるうちに蕁麻疹が広がっていきました。
私はすぐに症状を抑えるための緊急用の薬を飲ませ、かかりつけのアレルギー科の先生のところに連れていきました。
え!?卵白の成分が卵黄に移行する?!
病院に連れていき、自宅でかたゆでの卵黄を食べさせたところ蕁麻疹が出たことを伝えると、息子に与えたゆでたまごについて先生からいくつか聞かれました。
ゆで卵は作った後、時間が経つと卵白の成分が黄身の方に移行してしまうんです。
なので、出来上がったあとはすぐに殻をむいて、白身と黄身を分離させなければいけないんです。
もし、作って時間をおいたたゆで卵を食べさせて症状が出た場合は、本当に黄身でアレルギー反応が出たのか、それとも黄身に移行した卵白の成分でアレルギー反応が出たのかが正しく判断できないんです。
まあ、今回は作ったものをすぐに食べさせたということなので、ちゃおず君は卵黄に反応したんでしょう。
やはり卵黄はまだ与えずに、完全除去を続けましょう」
正しい「かたゆで卵黄」の作り方まとめ
以上の私の経験から、正しいアレルギー判断をするための「かたゆで卵黄」の作り方をまとめておきます(^^)
まず、食べさせるゆで卵は作りおきはしないこと。
前の日の夜に作っておいて殻をむかずに冷蔵庫に保存しておいたり、子供が寝ている間に作って2~3時間後に殻をむいて朝食時に与えるなどの作り方をすると卵黄部分に卵白の成分が移行している可能性があります。
必ずお子さんに食べさせる直前に作り、茹で上がったらすぐに殻をむき(と言っても茹で上がってすぐの卵ってめちゃめちゃ熱いですから、水で冷ます程度の時間は問題ないですよ(^^))、白身と黄身を完全に分離させてください。
そして、量は必ずキッチンスケールで測ること。
「3gって大体これくらいかなー?」
という目分量で摂取させると、症状が出たときに何gまで食べられたのか正確性に欠けます。
私はタニタのコンパクトな測りを使っています。
これだと台所に置いておいても全然邪魔にならないので(^^)
それから、ゆで卵は中央部まで完全に熱が通るように十分な時間加熱してくださいね。
沸騰してから最低13分以上は加熱するようにしましょう。
除去が解除されて、自宅で卵黄を与えることになったときなどの参考にされてみてください。
関連記事
→卵黄と卵白、加熱の有りなしでもアレルギーの強さは変わる
→負荷試験ってどんな風にするの?【ちゃおずの卵黄負荷テスト体験記】
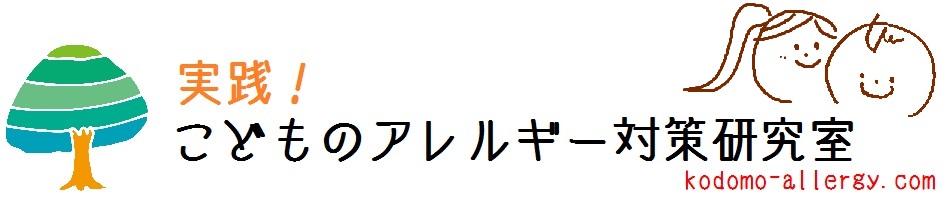
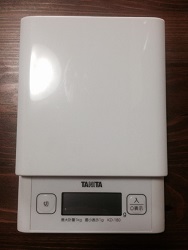










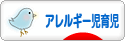





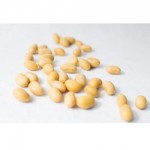











はじめまして。
ブログ拝見させていただきました。
うちは、乳製品アレルギー、花粉症、ダニ、ネコアレルギーです。
色々と勉強になります。
はじめまして。
ブログ訪問&コメントありがとうございます!
うちは卵・ダニ・動物全般(恐らく)アレルギーとアトピーです。
私自身もまだまだ勉強中ですが、ためになる記事を書けるように頑張っていこうと思います(^^)
どうぞよろしくお願いします!
10ヶ月の我が子は、アレルギー科で玉子アレルギーが判明しました。先生は、少しずつ食べさせていいと言われましたが。。勇気がいります。。。なんで玉子アレルギーに!!??って思ったりしますが。。はー。背中には先日した皮内テストのあとが。。まだブツブツが残ってるけど。。
こんにちは。
コメントありがとうございます。
そうですよね。「少しずつ食べさせていい」と言われても勇気がいりますよね…。
わかります。
担当の先生はアレルギー専門医、もしくは小児科とアレルギー科をかかげられている方でしょうか?
私は担当の先生に食べさせても大丈夫な細かい量(0.5g単位に教えてくださります)や茹でる時間、調理のときの注意点を指導してもらいながら少しずつ食べさせています。
細かい指導をしてくださる先生のもと進めれば、少しは不安もなくなるかもしれません(^^)